こんにちは。隈本です。
前回、司法書士の報酬についてお話をしました。
今回は、登記等で、報酬と必ずセットで出てくる、「登録免許税」のお話をしたいと思います。
登録免許税とは、不動産を購入・新築したり、会社を設立したりする際、それらの登記を法務局に申請しますが、その申請と同時に納める国税のことです。
登記税となっていれば、分かりやすいのでしょうが、不動産や会社の登記ばかりでなく、船舶の登記、航空機の登録、著作権・出版権の登録、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の登録、漁業権の登録、弁護士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・司法書士・建築士などの登録、金融機関・信託会社の事業免許、宅地建物取引業・建築業の免許など、50あまりの項目での登記・登録・免許などに関する税金を総合的に規定しているためです。
つまり、正式にいいますと、以下のような利益に着目して課税されるものをいいます。
①不動産等の財産権その他の権利の創設、移転、変更又は消滅等の登記等により、
第三者に対する対抗要件を備える等その権利が保護される利益
②法令の規定により個人について一定の資格(医師、弁護士、司法書士、公認会計士等)
が与えられ、特定名称の独占又は特定業務の独占が認められる利益
③個人資格の登録でなくとも、行政庁の免許、許可、認可等を事業開始の要件とする場合
(銀行業、地方鉄道業、宅地建物取引業等)において、当該事業の免許等から受ける独
占的、排他的な利益
実は、この登録免許税、以外と馬鹿にならない額になります。
「司法書士に登記を頼んだら数十万円も取られた」という話もよく聞きますが、大抵は、その内訳は、登録免許税の方が数十万円かかっており、司法書士の報酬(手数料)は数万円であるということもめずらしくありません。
例えば、不動産登記の登録免許税は以下のようになっています。
・所有権移転登記 売買 2.0% (不動産の価格の)
相続 0.4% (不動産の価格の)
・所有権保存登記 0.4% (不動産の価格の)
(建物を新築したときなどの最初の登記)
・抵当権設定登記 0.4% (債権金額の)
(住宅ローンを借りた場合など)
※住宅用家屋の軽減措置あり
・所有権移転登記時の軽減
一定の新築住宅または中古住宅を取得した場合 0.3%
・所有権保存登記時の軽減
一定の住宅を新築または建築後未使用のものを取得した場合 0.15%
・抵当権設定登記時の軽減
一定の住宅を取得するための貸付けに対するものの場合 0.1%
もう少し分かりやすいように、具体的に計算してみましょう。
1000万円の土地を売買すると、その所有権移転登記申請では、
1000万円 × 2.0% = 20万円
20万円の登録免許税が必要です。
(ちなみに、その際の司法書士の報酬(手数料)は、4〜6万円位だと思います。)
また、銀行から2000万円を借り入れた場合にする抵当権の設定登記申請では、
2000万円 × 0.4% = 8万円
8万円の登録免許税が必要です。
(ちなみに、その際の司法書士の報酬(手数料)は、3〜5万円位だと思います。)
上記のように、登録免許税額の基となる課税標準は、固定資産税などと同じく各市町村役場の固定資産税台帳に登録された価格となります。また、抵当権の設定登記などの場合には債権金額が課税標準となります。
この固定資産税台帳に登録された価格ですが、宮崎市ですと、宮崎市役所で、「固定資産評価証明書」というものを取り寄せると(発行手数料が数百円必要です)、評価額が記載してありますので、その額が課税標準となるわけです。
ところで司法書士は、依頼を受けた不動産登記のために、その方の「固定資産評価証明書」を取得することができます。
そのためには、法務局発行の「固定資産評価証明交付依頼書」が必要で、法務局で押印をもらうことで、手数料なしで、市役所から「固定資産評価証明書(不動産登記用)」を交付してもらうことができます。
ただし、これは、登記手続のためのみに用いることができます。
(スタッフ作)

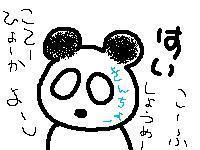


それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。
'09.11.30(Mon.)



